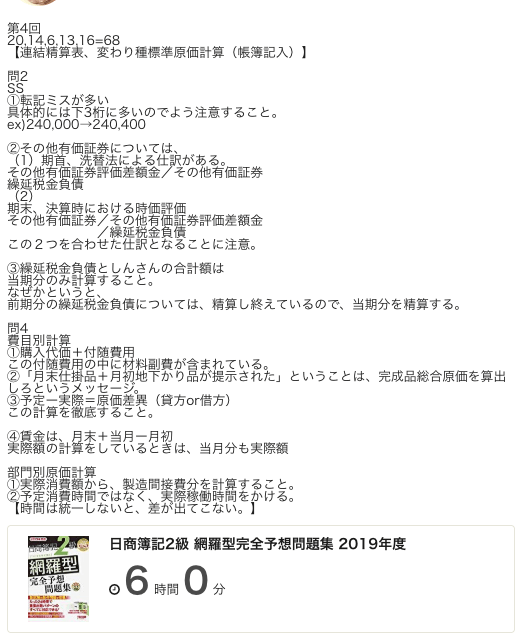「解説を丁寧に読み込むこと」と「凡ミスを極力減らすこと」が重要です!
- 投稿者:みかづきさん
- 勉強形態:通信
- 受験回数:3回
- 勉強期間:約1年
はじめに
現在、仕事をしていなくて学習専念中ですが、事務の仕事などの転職に生かせるように、簿記の勉強を始めました。簿記は未経験からのスタートでした。勉強方法は、通信教育(キャリアカレッジジャパン)を選び、2018年3月から3級の勉強を開始しました。
使用した教材と電卓
- キャリアカレッジジャパンのテキスト(3級&2級)
- キャリアカレッジジャパンの問題集(3級&2級)
- キャリアカレッジジャパンの添削問題(3級4回分・2級4回分)
- スッキリとける日商簿記2級 過去+予想問題集(TAC)
- 日商簿記2級 網羅型完全予想問題集(TAC)
- 第150回をあてるTAC直前予想 日商簿記2級(TAC)
- 仕訳問題(簿記検定ナビ)
- 予想問題(簿記検定ナビ)※第150回~第152回までの3回分
- 電卓 JF-S200(CASIO)
基本テキストは、キャリアカレッジジャパン(3級・2級セット)のものを使用しました。ちなみに、3級は3か月ほどの勉強で、第149回試験で一発合格することができました。
キャリアカレッジジャパンのテキスト(80点)
元々映像講義とセットで勉強するように作られているためか、自習するには少し分かりにくいときがあったので、マイナス20点にしました。
内容については、1級の範囲にまで踏み込んでいる部分がいくつかあり、上位級を目指す人には勉強になると思います。解答用紙が別冊でついているので、問題を解くときに役立ちました。入院中にこのテキストを商業簿記は4周、工業簿記は3周しました。
キャリアカレッジジャパンの問題集(80点)
総復習のために基本テキストを全て2周してから勉強しました。
テキストの練習問題のような感じで、各単元に対応する問題量はページ数のわりにそれほど多くないように感じました。病院で自習するにはちょうどよい量でしたが、実際にはもう少し多めでも良かったかなと思います。
それから、解答解説が問題のすぐ後に書かれているので、別冊になっているとさらに良かったと思います。解説を読んでも分からなかったところは、質問でカバーできたので問題ありませんでした。
なお、こちらもテキストと同様に解答用紙が別冊でついています。
キャリアカレッジジャパンの添削問題(80点)
入院中に2級の添削問題を解きました。テキストや問題集では触れていなかった内容もいくつかあり、解き方が分からなかったのでその頃は難しく感じました。
添削後は解説と一緒に答案が送られてきます。こちらも分からないところは質問で解決しました。
スッキリとける日商簿記2級 過去+予想問題集(90点)
過去問は最初やり始めたときは解説が少なめで、もう少し丁寧に書かれていれば良いのにと思いましたが、1年近く勉強した結果、問題を解き慣れてきた頃には知識が身についてきたのか、この解説の量で解けるようになっていました。解説は無駄がないため、最初は物足りなく感じるかもしれません。
予想問題は少しボリュームが多いものもあり、最初は2時間で解けないこともありました。巻末についていた日商提供のサンプル問題は、税効果会計など問題も豊富で新論点の対策にもなりとても役立ちました。
日商簿記2級 網羅型完全予想問題集(90点)
この問題集は全体的に難しめで、それぞれの論点が網羅的に全て載っているため、自分の苦手な論点を見つけたりいろいろなパターンの問題に触れたりするには良いと思います。
私はテキストで基本を学んだ後にすぐやりましたが、応用力が身についていないためにボロボロでした。この問題集を繰り返しやることでだいぶ力がついたので試験対策に役立ちましたが、各回によって難易度に少し偏りがある気もしたのでマイナス10点です。
第151回をあてるTAC直前予想 日商簿記2級(90点)
ネット上で、この「あてる」をやっておけば安心というのをよく聞くので購入しました。実際の試験よりも難しめに作られているという話ですが、確かにこれをやっておいたおかげで実際の試験でも得点できた問題がありました。
第150回・第151回試験は市販の問題集には載っていない問題が多かったので、結果的には合格に結びつきませんでしたが、この問題集のおかげで応用力はだいぶ身についたように思います。
仕訳問題(簿記検定ナビ)(100点)
特に第150回試験対策でお世話になりました。全ての仕訳問題を時間を決めて毎日取り組みました。基本の仕訳問題でできなかった問題を振り返ることで、それまで気がつかなかった自分の弱点や苦手な論点などの対策になりました。
予想問題(簿記検定ナビ)(100点)
この予想問題は毎回楽しみにしていて、いつも試験前に一通り他の問題集の復習が落ち着いてから一度、本番を意識して解いていました。70点ぎりぎりとれないときもありましたが、サイトに掲載されている解説がとても丁寧に書かれているため、理解しやすく勉強になりました。いつも2~3周していました。
電卓 CASIOのJF-S200(100点)
1級の勉強をする前に、クレアールの講師の方が「1級では、工業簿記で√キーを使うところがある」とおっしゃっていたので、√付きの電卓に買い換え、この電卓を2級受験時にも使用しました。
その前に使っていた電卓もCASIOだったため、使いやすいように数字の並びなどが同じものにしました。キーを打つときの音も前の電卓よりも静かで使いやすく、比較的安価なのでおすすめできます。
1回目の受験(2018年7月~11月)
3級合格後、しばらくして7月から入院することになり、病院で2級の学習をスタートしました。教材を病院に持ち込んで、体調の良いときはひたすらテキストを読み込んで、1日2~10時間ほど勉強しました。
入院中の学習では、分かっても分からなくてもまずは一通り最後まで進めることに重点をおいて、繰り返しテキストを読んで、仕訳を覚える練習をしました。
3級と違ってすぐには頭に入らず、仕訳のパターンに慣れるのに苦労しました。特に税効果会計や連結会計はなぜそうなるのか分からず、なかなか知識が定着しませんでした。
映像講義は、退院してからまとめて見ましたが、教材を予習のような形で先に勉強していたので、後から復習のような形で講義を見ることができて頭に入りやすかったです。また、郵送による質問制度もあったため、フル活用して理解を深めていきました。
その後、退院前に過去問題集を、10月の退院後の落ち着いた頃に予想問題集を買いました。退院後は自宅で勉強することが多く、簿記ナビさんのサイトを見つけて、仕訳問題や予想問題など活用させていただきました。
過去問は慣れるまでなかなか点数がとれなかったのですが、繰り返し解くうちに7割以上とれるようになってきました。網羅型は難しく、1回目は30~50点ほどで、解説を読んでもなかなか理解できない部分が多かったのですが、徐々に50~70点台ぐらい取れるようになりました。
網羅型で思うような点がとれなかったため、前日もあまり寝られず、当日も不安が残りました。第150回試験は初見の問題が多く、また緊張しすぎてしまい、他の受験者の電卓をたたく音が気になって集中できず、それぞれの問題に時間がかかってしまって68点で不合格でした。
2回目の受験(2018年12月~2019年2月)
12月は日商PC検定など、他の資格取得に向けて勉強していたため、実質1~2月の2か月間の勉強でした。新たに問題集(TACのあてる)を追加しましたが、やはり最初は難しかったです。
とにかく問題をたくさん解くことを中心に勉強していたので、解説の読み込みより演習量を優先してしまい、あまり理解できていないまま解いていた気がします。本来は2時間で解く問題を1時間半で解くと決め、解き終わらなくてもそこでやめて答え合わせしていました。
第151回は比較的易しい第2問(株主資本等変動計算書)や第5問(等級別総合原価計算)で凡ミスをして大幅に失点してしまい、60点で不合格でした。
3回目の受験(2019年3月~6月)
3月に入り、簿記2級と並行して簿記1級の勉強も始めました。まだ2級も受かっていないのに…とも思いましたが、少しでも2級の理解の助けになれば、というのと、2級が受かったら1級も、と以前から思っていたからです。
1級も通信教育で、こちらはクレアール(WEB通信)を選びました。3~4月は1級の勉強を中心に、映像講義を見ながらテキストを進めました。
5月に入ってから2級に戻りましたが、今回は演習量よりも解説の読み込みに時間をかけ、完全に理解できるまで次に進まないようにしました。また、時間があるためについダラダラ勉強してしまいがちだったので、時間を決めて集中して勉強するようにしました。
試験日1日の流れ
試験前日は、疲れを残さないようにすることを優先し、あまり長時間勉強しませんでした。今回は不思議と落ち着いた気持ちで過ごすことができ、前回や前々回のときよりもよく眠れました。
試験当日の朝はいつも通り6時くらいに起きました。朝食もいつもと同じトーストとコーヒーと目玉焼きでした。2級の試験は午後からなので、午前中に過去+予想問題集の予想問題を1回分解きました。
試験会場は車で1時間ほどの場所で、母に車で送ってもらいました。1時間前には着く予定で出かけたので、12時には会場に着きましたが、まだ誰も来ていませんでした。
会場には、キャリアカレッジジャパンの基本テキストを2冊(商業簿記・工業簿記)持っていき、始めから全体を流し読みしていました。読んでいるうちに時間が経ち、だんだん他の受験生も来始めたので、待っている時間を長いとは思いませんでした。
13時30分になり、試験官から簡単な説明と答案用紙に名前等を書くよう指示されました。
13時40分 試験開始!
今回は「1→4→5→2→3」の順で解くことにしました。今回の第1問・仕訳問題は前回・前々回と比べて解きやすく、落ち着いて解き始めることができました。
ただ、問2で前払利息勘定がなかったため焦り、見直しのときも変に前払利息にこだわってしまい(間違っても良いから何か書いておいた方が良いと思えず)、支払利息ではなくそこだけ空欄のまま提出してしまいました。
第4問はすんなり終えて、第5問へ。第5問はなぜか途中で頭が回らなくなり、解いているうちに変な勘違いをしてしまったように感じ、見直しの時間でもう一度後でその問題をやると、やっぱり違っていました。
第2問は今まで見たことのない感じに見えましたが、落ち着いて問題を読むと普通に解ける問題でした。
第3問は税効果会計が入っていましたが、仕訳自体は何とかできました。でも、実際に計算してみると合計が何回やっても合わず時間がかかってしまったので、できるところまでやって見直しにかかりました。
今回は前回・前々回よりも落ち着いて解くことができ、周りを気にせずマイペースに取り組めたのが良かったです。解答速報を見るまでは緊張しましたが、無事合格点に達していて、結果的には73点で合格できました。
まとめ
今回、5~6月にかけて集中して2級の復習をする中で「解説を丁寧に読み込むこと」と「凡ミスを極力減らすこと」の大切さを感じました。
今回の152回試験も結局は凡ミスがいくつもありましたが、限られた時間の中で(後でやり直しをしなくて済むよう)いかに丁寧に問題を解くかというのが大事だと思いました。
それから、私は体調に波があるので、眠気があるときは無理せず休むようにして、その分、勉強できる時間に集中するよう心がけました。
簿記ナビさんの仕訳問題は仕訳力アップにとても役立ち、予想問題も毎回必ず解いていたおかげで、いろんな問題にあたって応用力をつけるのに役立ちました。ありがとうございました。
管理人からみかづきさんへ追加の質問
| 2級の勉強を始めるにあたって、キャリアカレッジジャパンの通信講座を選んだ理由を教えてください。また、他の方にもおすすめできますか? | |
| ちょうど勉強を始めようと思っていたときに、キャリアカレッジジャパンのカタログの中で簿記の通信講座があるんだというのを知ったのがきっかけでした。
それまでは、通信講座を受けたことがなく、簿記というものの存在も知らなかったのですが、3級・2級がセットになっていて効率的に勉強できそうということと、近くに予備校などがないため家にいながら映像講義などで授業が受けられるというのと、何度でも質問無料という制度があったのでこの通信講座に決めました。 また、不合格なら「全額返金」サービスや、合格したら「2講座目無料」サービスなどもあり、始めやすそうだというのもありました。 他の会社の通信講座を調べずにすぐに決めたので、後になってから簿記ナビさんの合格体験記を読んで、他にもいろいろな通信講座や予備校があるんだという事を知りました。 教科書は映像講義を担当する講師の方が作っているようで、映像講義に対応するように作られているため、病院での自習などでは少し頭に入りづらい部分もありましたが、映像講義とセットで聴きながら勉強すると分かりやすいと思いました。 映像講義の単元が細切れになっているので集中して聴くことができ、また講師の方が身近な例や雑談なども交えて教えてくださったので分かりやすかったです。 質問は、郵送・Fax・メールで受け付けていて、病院では携帯電話が使用禁止だったため、自習中に分からなかったところをまとめておいてあとで郵送で質問しました。返送も早く、講師の方からの励ましの言葉なども添えられていて、やる気につながりました。 他の通信講座や予備校のことは分からないため比較はできませんが、対応も親切で丁寧に指導していただいたのでおすすめできます。 |
| 1級の勉強を始めるにあたって、クレアールの通信講座を選んだ理由を教えてください。また、他の方にもおすすめできますか? | |
| 費用が比較的安かったのと、担任制になっていて勉強中困ったらすぐに担任の方に相談できるというのと、毎日電話で無料で質問できる(郵送・メール・Faxもあります。)サービスがあったのでクレアールにしました。
始めてから半年ほど経ったものの、1級は範囲がとても広く、2級や他の資格の勉強もしていたために、実際には1級の勉強はあまり進んでいません。今のところはまだ何とも言えませんが、映像講義を見ながら勉強していて分からなかったことを時々電話で質問したりしています。 曜日・時間などは決まっていますが、講義担当の講師の方に電話で直接質問ができるのはとても良いと思います。 授業だけの一方向でなく直接講師の方とやり取りできるので、スムーズに理解できます。試験前には直前答練や公開模試もあり、自分の実力をはかることもできます。キャリアカレッジジャパンと同様におすすめできます。 |
| みかづきさんの得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |
| 得意な論点というのはあまりなく、まんべんなく勉強しているうちにだんだんできるようになっていった感じです。商業簿記は有価証券や固定資産など、工業簿記は標準原価計算や総合原価計算などです。
苦手な論点は商業簿記の連結会計、工業簿記の直接原価計算でした。連結会計は仕訳の意味が分からず、記憶する量も多かったため、最初は全く理解できませんでした。そのため、まずは仕訳自体を覚えることから始めました。 自習だけでは分からなかったのが、映像講義を見て徐々に分かるようになり、仕訳を覚えてからはパターンで対応できるというのが分かり、問題集の問題での得点率も上がってきました。 直接原価計算は、いろいろな問題にあたることで解き方を身につけていきました。特に直接原価計算から全部原価計算に変換する問題は苦手意識があり、分からなかったので最初は放置して他の問題で得点できるようにと思っていました。 最終的には、まんべんなくとれるように苦手な部分にも向き合って、とにかく解説を読み込み、1つ1つ理解しながら解き方自体を覚えこむつもりで、何度も復習しました。 |
| みかづきさんの、勉強期間中のモチベーションの維持方法を教えてください。 | |
| 簿記ナビさんの合格体験記を読んだり、合格後に実際に仕事に生かしていることなどをイメージしたりしていました。合格体験記には自分の知らない勉強法が載っていたり、独学で頑張っている人たちもたくさんいることが分かり、また、試験当日の様子なども参考になりました。
勉強をしたくないときや体調が思わしくないときは思い切って休んで、調子のよいときや集中できるときにまとめて勉強するようにしていました。 |
| 2019年3月から1級の勉強を始められていますが、3月以降、2級の内容が易しく感じられるようになりましたか? | |
| クレアールの商業簿記の1冊目のテキストは、初めの方は2級の復習を兼ねた内容が多めだったため、1級とはいえ新しい論点にはその頃はまだあまり触れることができませんでした。
1級は1級で新しい内容を学習していくので、2級と絡めて勉強するという感じではなかったように思います。 しばらく1級やその他の資格の勉強だけをしていて、後で2級の復習に戻ったときに、1級はまだ初めの方ではありますが、1級の難しさや複雑さに比べると、2級の方がだいぶ内容も分かりやすかったように感じました。 |
管理人コメント
みかづきさん、簿記2級試験の合格おめでとうございます。また、合格体験記をご投稿いただきありがとうございました。
最後のまとめのところで「解説を丁寧に読み込むこと」と「凡ミスを極力減らすこと」の重要性を指摘していただきましたが、私も同感です。
なんとなく時間を計って問題を解いて、なんとなく採点して、なんとなく復習してもなかなか力は付きません。毎回、目的意識を持って問題に取り組み、間違えたところ・分からなかったところを放置せずにその都度、きちんと復習して解法をマスターすることが重要です。
文字にすると当たり前のことですが、(受験生時代の私も含めて)意外と出来ていない方が多いです。たくさん問題を解いているのになかなか点数が伸びない、という方はぜひみかづきさんを見習って、ご自身の勉強スタイルを見直してください。
みかづきさんが使われた教材や電卓のまとめ
- 教材:キャリアカレッジジャパンの通信講座の教材
- 過去問題集:スッキリとける 日商簿記2級 過去+予想問題集
- 予想問題集:日商簿記2級 網羅型完全予想問題集
- 予想問題集:第151回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級
- 電卓:CASIO JF-S200
- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。